商標登録で立ちはだかる壁『拒絶理由』とは?
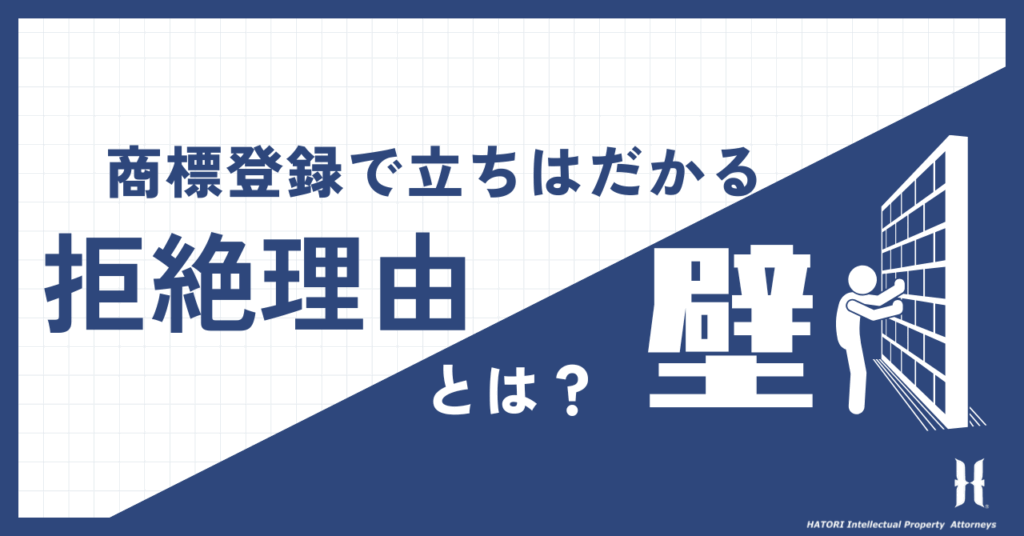
「商標は出願すれば自動的に登録されるんでしょ?」
そう思われている方も少なくありません。
しかし実際には、特許庁の審査を通過しなければ登録は認められません。その過程で大きな壁となるのが 『拒絶理由』 です。
商標出願から登録までの流れ
出願を行うと、特許庁の審査官が「この商標を独占的に使用させてよいか」を商標法に基づいて審査します。
要件を満たさないと判断された場合、出願人には 拒絶理由通知 が届きます。
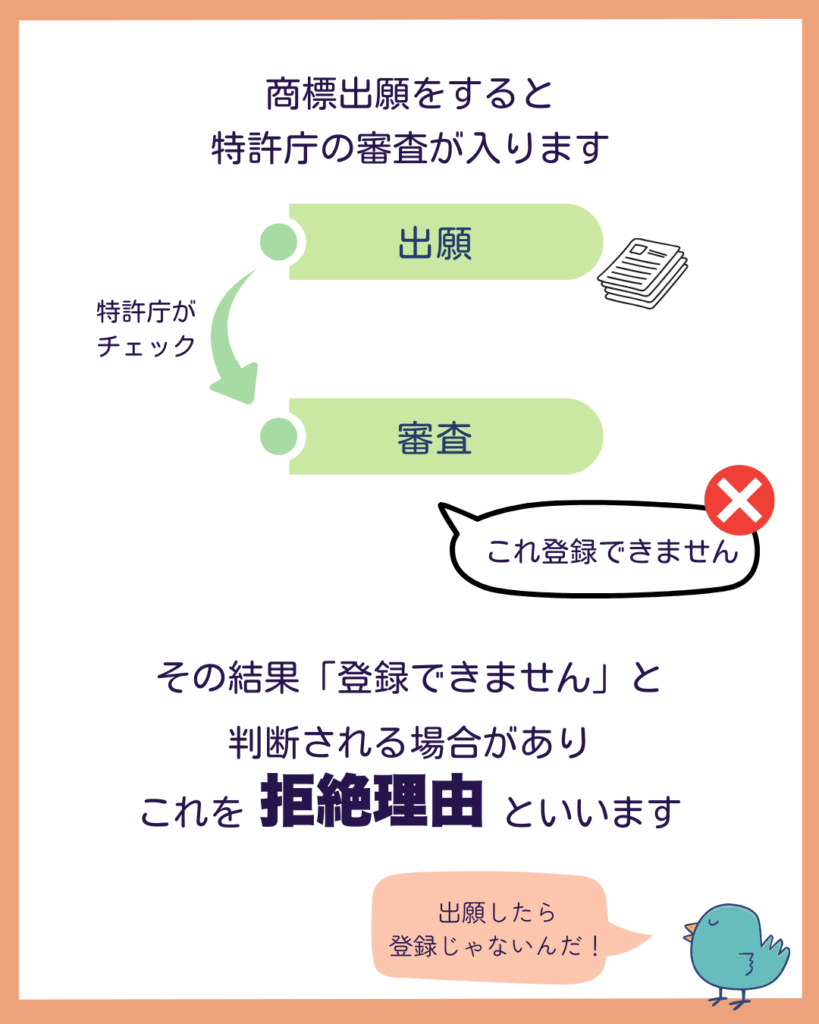
ただし拒絶理由が出たからといって、登録の道が完全に閉ざされるわけではありません。
意見書や補正書で説明を行うことで、登録につながるケースも多くあります。
よくある拒絶理由の例
1. 他人の商標と似ている場合(商標法第4条第1項第11号)
拒絶理由の中でも、出願人の方が特に直面しやすいのが「既に登録されている他人の商標と似ている」というものです。
審査官は、
・ 見た目(外観)
・ 読み方(呼称)
・ 意味(観念)
の三つの観点から、出願された商標と先行商標を比較します。
例えば、ある製薬会社が「ハトキク」という商標を薬品について出願したとします。
一方で、既に「ハットキク」という名前が同じ薬品について登録されていたらどうでしょうか。
消費者からすれば、店頭で「ハットキク」と「ハトキク」が並んでいたら「同じ会社の商品かな?」と誤解して購入してしまうかもしれません。
医薬品の例でいえば、たった1文字の違いでも誤解が大きなリスクにつながります。
これは医薬品に限らず、食品や化粧品、アパレルなど 日常的に選ばれる商品・サービス全般 にも同じことがいえます。
「少し違うから大丈夫」という自己判断は危険であり、実際には登録が認められないケースも少なくありません。
せっかくブランドに投資をしても、商標登録が下りなければ看板やパッケージを掛け替えるなど、大きな負担が生じてしまいます。
だからこそ、出願前の調査や専門的な類否判断がとても重要なのです。
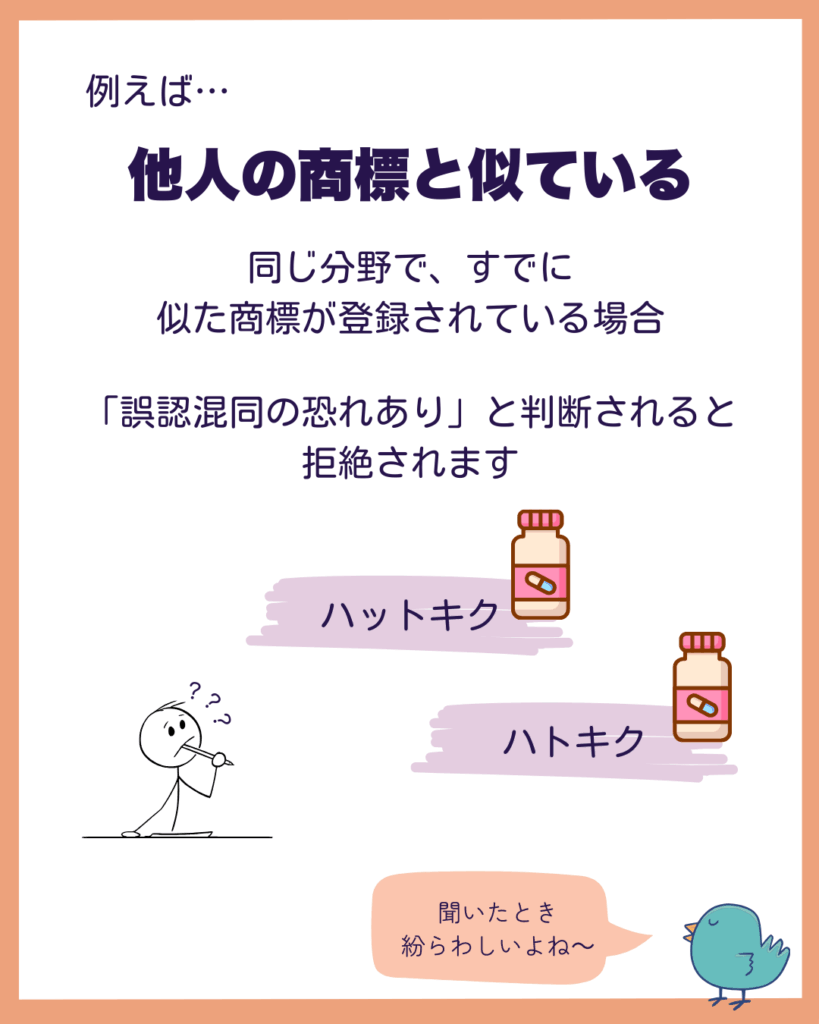
2. 説明的すぎる場合(商標法第3条第1項第3号)
商品の性質や特徴を直接的に示す言葉は、原則として商標登録できません。
例:
・ 清酒に「吟醸」
・ 洋服に「WOOL」
・ 入浴剤に「疲労回復」
・ 飲食物の提供に「セルフサービス」
これらはいずれも「商品の品質や特徴」「サービスの提供態様」を説明するだけの一般的な表現です。もし一社が独占できてしまったら、他の事業者が自由に説明できなくなり、市場の公平性が損なわれてしまいます。
ただし、長年の使用で「この言葉=この会社」と消費者に認識されるほど定着すれば、例外的に登録できることもあります(使用による識別力の取得)。
しかしそのためには広告実績、売上資料、メディア掲載など膨大な証拠を提出する必要があり、中小企業にとっては現実的にハードルが高い場合が多いです。
「わかりやすさ」だけでなく、「ブランドを示す力」があるかどうかを意識してネーミングすることが重要です。
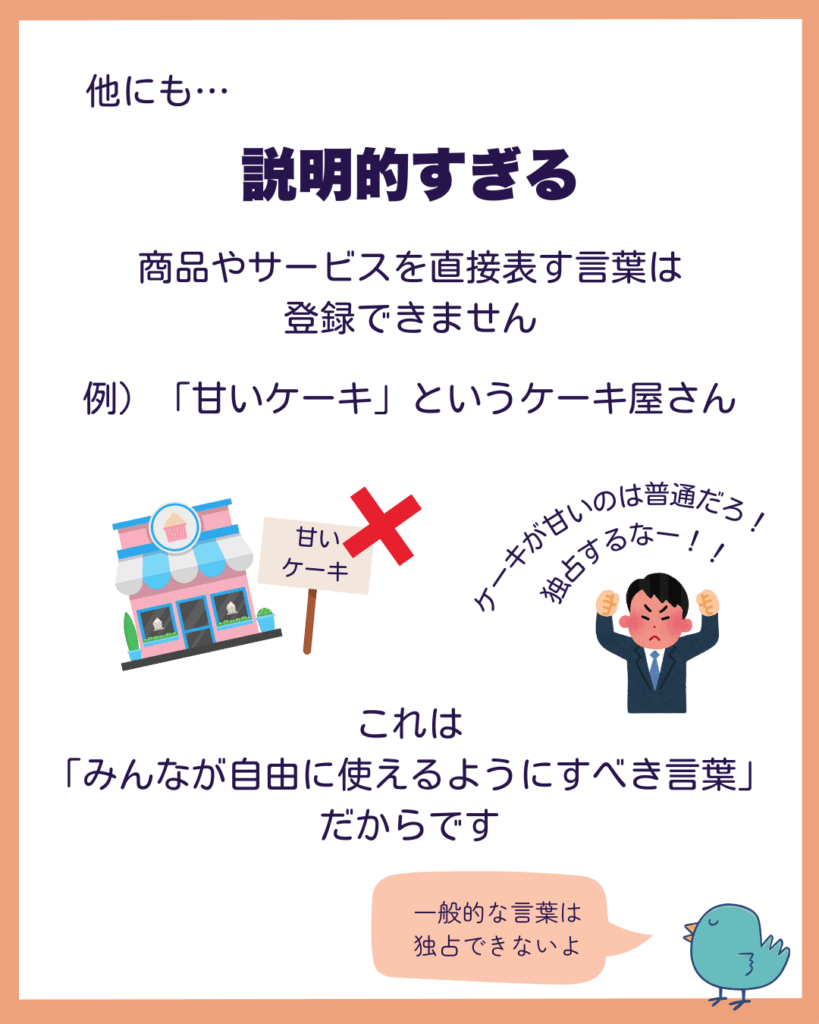
3. 公序良俗に反する場合(商標法第4条第1項第7号)
見落とされがちですが、社会の一般的な感覚に反する表現も拒絶されます。
例:
・ 差別的な意味合いを含む言葉
・ 卑猥な表現
・ 他人を侮辱するフレーズ
また、宗教・歴史・文化に密接に関わる言葉を不用意に使うこともリスクがあります。
特定の神仏や歴史的人物を商品名に使うと、不敬だと受け取られる場合もあるのです。
これは単なる法律上の規制ではなく、ブランド自体の信用や社会的評価に直結する問題 です。登録が認められないだけでなく、企業イメージを損なう危険があるため注意が必要です。
拒絶理由を乗り越えるには
拒絶理由通知が届いたとしても、必ずしも登録の道が閉ざされるわけではありません。
重要なのは「事前の準備」と「通知後の適切な対応」です。
① 出願前にできる対策
・ 商標調査の実施
先に登録されている商標と似ていないかを確認することが、リスク回避の第一歩です。
似ている商標が存在する場合、区分(商品・サービスの分類)を工夫したり、別のネーミングを検討することができます。
・ ネーミングの工夫
「説明的すぎる表現」や「誰でも使いたい言葉」は避けることが重要です。
単純な特徴を表すだけではなく、自社の独自性やストーリーを込めた名前にすることで、審査を突破しやすくなります。
② 拒絶理由通知を受けた場合の対応
通知が来てもすぐに諦める必要はありません。
・ 意見書の提出
審査官の判断に対して「この商標は類似しない」「識別力がある」といった法的な根拠を示すことで、登録に至る可能性があります。
・ 補正書の提出
出願した商品・サービスの範囲を限定するなど、修正を加えることで拒絶理由を解消できる場合もあります。
・ 証拠資料の提出
長年の使用によって消費者に広く認識されている場合、その実績を資料で示すことで登録可能になるケースもあります。
まとめ
商標登録は、出願すれば必ず通るものではありません。
ただし、拒絶理由が出ても「意見書」「補正書」「証拠資料」などで対応することで、登録につながる可能性は十分にあります。
大切なのは、
・ 出願前にどの程度リスクがあるのかを把握すること
・ 通知が届いた際に冷静かつ戦略的に対応すること
この両方をスムーズに進めるためには、専門的な知識と経験が欠かせません。
重要なのは、出願前にリスクを見極め、通知が届いた場合には冷静かつ戦略的に対応することです。
商標登録は専門家にご相談ください
商標は、会社やお店の「顔」であり、長期的に育てていくブランド資産です。
しかし、その登録の道のりには法律的なハードルが多く、個人で乗り越えるのは容易ではありません。
当事務所では、
・ 出願前の簡易商標調査
・ ネーミング段階でのアドバイス
・ 拒絶理由通知への対応(意見書・補正書の作成)
まで一貫してサポートしています。
「せっかく出願したのに登録できなかった」
そんな事態を避けるためにも、まずは一度ご相談ください。
群馬県で特許・商標・意匠に強い弁理士をお探しなら、当事務所へ。
豊富な経験と実績を活かし、お客様の大切な知的財産を確実に保護いたします。
【群馬県で知的財産の商標・特許・意匠のことなら】
羽鳥国際特許商標事務所
所長/弁理士 羽鳥 亘
副所長/弁理士 羽鳥 慎也
弁理士 柿原 希望
