売れなかった野菜が「ブランド」になった日

「形が悪い」「ちょっと傷がある」味は変わらなくても、見た目だけで値が下がる野菜があります。
JAみなみ信州は、そんな野菜に名前をつけることで価値を変えました。
名前がつくと、愛される
1980年代、同組合が初めて商標登録したのは「きらめき」。果実につけたこの名前が、知財活用のはじまりでした。
そこから次々に生まれたのが、「曲がりなりにもキュウリです」「ごめんナスって」などユニークな名前。

J-Jpatpatより引用
商標登録第5140055号
商標登録第5118557号
一見ネタのようでも、消費者の印象に残り、「売れにくい野菜」が「選ばれる商品」に変わっていきました。
名前が物語を与え、価値をつくったのです。
商標がブランドの土台になる
JAみなみ信州では、商標を「飾り」ではなく品質を保証する仕組みとして使っています。

JAみなみ信州ホームページより引用
糖度が一定以上の果物だけに付ける 商標第3269186号「太鼓判」、
特に品質の高いぶどうだけに使う 商標第6229829号「輝房(きぼう)」。
こうした商標は、単なる区別のためではなく、「安心して買える目印」として機能しています。
ブランドを支えるのは、名前と信頼。その信頼を長く保つために、商標という仕組みで守ることが欠かせません。
弁理士の目線で見ると
JAみなみ信州の取り組みの良いところは、現場のアイデアを、知財の仕組みで支えていることにあります。
販売の現場から生まれるネーミングは、消費者の心をつかむ力があります。
一方で、インパクトが強い言葉ほど真似されやすい。
だからこそ、思いつきで終わらせず商標登録という形で守ることが大切です。
名前を守る仕組みを持つことで、地域の発想が一過性で終わらず、次の世代へ受け継がれていきます。
知財とは、創意を長く活かすための道具。それを上手く使える地域ほど、ブランドを「育て続ける力」を持っているのです。
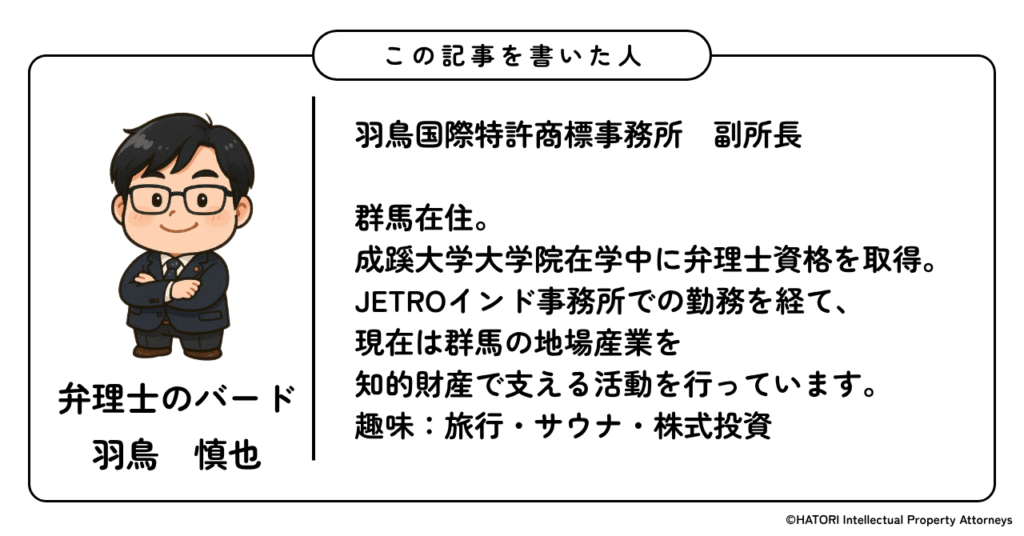
羽鳥国際特許商標事務所より
商標登録は、名前を守るための手続きにとどまりません。
その先にあるのは、「どう使い、どう育てていくか」を考えることです。
私たち羽鳥国際特許商標事務所は、地域の特産品や企業のブランドが、長く信頼される存在になるよう
登録の段階から運用、活用まで、それぞれの現場に合った形でサポートしています。
名前を守ることは、その土地や人の想いを未来につなげること。そうした知財の力を、これからも地域とともに育てていきます。
群馬県で特許・商標・意匠の取得をお考えの方は、弁理士 にご相談ください。
当事務所では、お客様の知的財産をしっかりと保護し、ビジネスの成長をサポートいたします。
~群馬県で知的財産の商標・特許・意匠のことなら~
羽鳥国際特許商標事務所
所長/弁理士 羽鳥 亘
副所長/弁理士 羽鳥 慎也
弁理士 柿原 希望
note:https://note.com/hatoripat
Instagram:https://www.instagram.com/benrishi_bird/
YouTube:https://www.youtube.com/@bird_ip
この記事は、特許庁発行
『商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド」
– ビジネスやるなら、商標だ!(2024年版)』を参考に作成しています。
